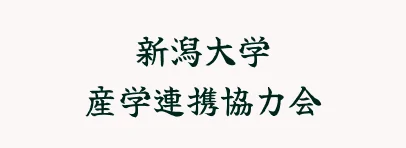社会基盤
2025.05.15
ボーリング情報による沖積平野の地盤モデル構築と広域の地盤災害予測への展開
工学部 社会基盤工学プログラム
地盤工学研究室

保坂 吉則
HOSAKA Yoshinori
自然科学系 助教
研究の目的、概要、期待される効果
土木構造物や建築物の耐震化が進められていますが、近年の地震では地盤災害への対応の重要度が高くなってきました。その中で、2024年1月に発生した能登半島地震では、震央から150km以上離れた新潟市内で液状化被害が発生し、上部の構造体は十分耐震性の高い家屋でも大きな被害に至っています。
当研究室は、近年利用が可能となってきたボーリングのデータベースを用い、主に沖積層を対象とした表層地盤構造のモデル化を試みてその特性を把握した上で、地震時の地盤の危険度(液状化危険度や地盤増幅度、盛土安定等)の広域評価へ活用する方法や予測の高精度化を目的に研究を進めています。
ボーリングデータから液状化危険度や地盤増幅度を算定する手法はほぼ確立していますが、広域の評価にあたり、ボーリング情報が疎な地域や深層部のモデルの精度向上が課題となっています。そこで、ランダムに分布するボーリング点から得られる土質やN値、孔内水位等の情報に基づき、Kriging法などの空間統計学の手法を活用し、メッシュで広域を面的に網羅する適切な地盤モデルが構築できれば、様々な地盤災害のハザード評価への展開が期待されます.
なお本研究は,新潟大学共創イノベーションプロジェクトの社会インフラ・マネジメント共創IPに地盤工学分野の課題として参画しています.
関連する知的財産論文等
- ・地盤工学会編:全国77都市の地盤と災害ハンドブック,丸善出版,2012.(新潟市を担当執筆)
- ・保坂吉則:ボーリングデータベースに基づく新潟市域の表層地盤の粒度と工学的特性,地盤工学ジャーナル,Vol.13,No.4,pp.341-357,2018.
アピールポイント
北陸の液状化しやすさマップ作成に関与した経験がありますが、ほかにも長年研究してきた液状化をはじめとする地盤工学に関する知見を地域に還元したいと考えています。
つながりたい分野
- ・平野地盤に関する地震防災に取り組む自治体やインフラ管理企業等
お問い合わせは新潟大学社会連携推進機構ワンストップカウンターまで
onestop@adm.niigata-u.ac.jp