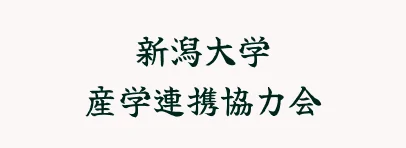私たちの生存基盤である地球表層の形状を探究する

- 専門分野
- 地形学、自然地理学、地理情報科学、地球人間圏科学、第四紀学
- キーワード
- 地表近傍境界域(クリティカルゾーン)、地理情報システム、人新世、未災、流域環境
研究の目的、概要、期待される効果
目の前にある地形はいつから・どのような過程をへて形成されたのでしょうか。さらに言えば、地球表層はなぜその形状なのでしょうか。この問いを明らかにするために、私は地理情報システムを駆使したフィールドワークを展開しています。
私は、折れ尺から加速器まで、問題解決のために最適な手法を選択した研究を推進しています。例えば、滋賀県・田上山地では、過度な森林資源の収奪により、斜面土層の完全な喪失が過去300年間に劇的に進行したことを山麓堆積物の宇宙線生成核種分析から明らかにしました(論文1)。山梨県・巨摩山地では、地すべり地形の発達史を組み立てるために踏査を重ねていたところ、年代決定の手掛かりとなる後期更新世の火山灰層や泥炭層を新たに発見しました(論文2)。
私たちが自然環境の恵みを享受するとともに、近未来に起きうる災害を認知して備えるには、地球表層の諸現象に関する空間的・時間的な入れ子状の階層構造を深く理解することが必須です。例えば、落雷が地表の形状を変化させるのは経験的に知られているものの、岩石の風化過程でどのように寄与しているのかは未解明です。地形の理解を通じて雷伝承を紐解くこと、ひいては身近な地域の魅力を掘り出すことに心を燃やしています。

滋賀県・田上山地の山地斜面.人為影響を免れた森林と土層の発達する斜面(A)と人為影響を受けた荒廃斜面(B)

樹木根系による付加的粘着力が発揮される場合(A)とそうでない場合(B)での斜面安全率. 滋賀県・田上山地の不動寺流域を例にArcGISで計算

関連する知的財産論文等
- 論文1: Ohta et al., Geomorphology, 2022 (DOI: 10.1016/j.geomorph.2022.108201)
- 論文2:太田ほか,第四紀研究,2025 (DOI: 10.4116/jaqua.64.2402)
アピールポイント
現地踏査・試料分析・地理情報解析を3本の柱として、課題解決に最適な手法を選択して研究を推し進めてきました。必要なスキルは実践的に習得してゆきます。ともに前進しましょう。
つながりたい分野
- 身近な自然環境の来し方と行く末を解明することを通じて、例えば、近未来の災害に備える、地域資源に付加価値を与える、といったようなことを検討されている方々と協働したいです。
お問い合わせは新潟大学社会連携推進機構ワンストップカウンターまで
onestop@adm.niigata-u.ac.jp